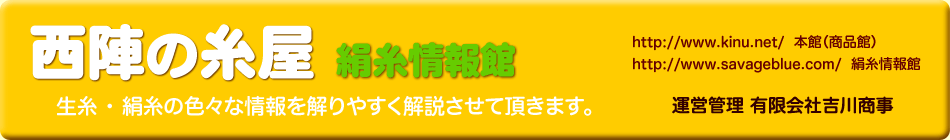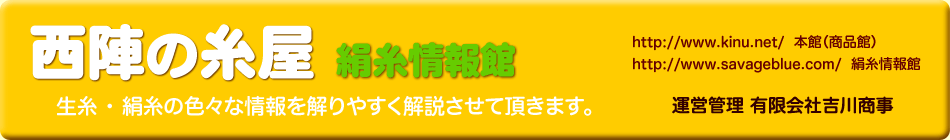手引き真綿糸のお話し
|
|
皆さんは手引き真綿糸をご存知でしょうか?
手引き真綿糸の特徴はふっくらとした軽い風合い、と繊維が比較的まっすぐ揃っている事によってでる光沢、そして人の手によってしか出来ない不均一な太細、等々で現在比較的手に入れることの出来る糸の中で、玉糸と並ぶ織物人気原料糸の一つです。
ではそれをどうやって製造しているか?
まずはたくさんの繭をお湯の中で無造作に引っ張り、そしてそれを何重にも積み重ねて固まりにして真綿を作っていきます。この時、何故かは解りませんが普通の繭玉以外に必ず玉繭を使用するみたいです。
ちなみに、、、
帽子のように丸い型の上に繭玉を広げ何重にも重ね合わせて出来た真綿を帽子真綿。
平面上に四角く繭玉を広げ何重も重ね合わせて出来た真綿を角真綿と呼びます。

その真綿を手でつまみ出しながら1本の糸にしていった糸が手引き真綿糸と呼ばれる物です。
製造時には糸繰り機を使って一定のスピードで巻き上げて行き
細い手引き真綿は微妙な繊度調整が難しく、逆に太すぎると原料(真綿)の減りが早くて難しいみたいです。
お客さまの中には、帽子真綿・角真綿を購入してご自分で糸を引いてかれる方がおられるみたいですが、
私もそこまでは体験した事が有りません。汗
ホント当店のお客さまは凄いです。びっくりです。
現在、何処かにはあるのでしょうけど、私の知っている限りでは日本で手引き真綿糸を生産する工場は無くなってしまいました。現在は結城地方ですら中国の手引き真綿&原料真綿が入っておりますので、、、
ちなみに現在日本でで売られている真綿はほとんどが中国製の手引き真綿糸です。
しかも現在真綿製造工場は1社のみですので今後もしかすると中国真綿もなくなる可能性が多いです。
私の勝手な想像では中国でも5年後に60%は製造してないかな?
■手引真綿糸の繊度表示
現在、使用されている手引真綿糸の繊度を表す単位には「回数と言う単位」と「匁(もんめ)」と言う単位があります。あまりご存じで無い方も多
いと思いますので詳しく説明しましょう。
●回数(かいすう)
古くから日本で使用されてきた単位
真綿糸は普通、枠周1.11mで1綛すが40gにするようにしてい
ました。
その時に何回枠を回っているか?がこの単位表示です。
数字が大きくなれば細くなります。
●匁(もんめ)
中国真綿に使われている単位
1匁あたり50デニールと計算されている方もいらっしゃるみたいですが、正確には約40デニールが正解みたいです。
だいたい解りましたでしょうか?
現在では中国から入ってきている手引真綿糸は何故か細い物は「匁表示(3~7)」太い物は「回数表示」で入荷されています?当店では3~5匁の絹糸を何故か匁表示で販売しております。笑
(昔から何故かそのように販売していたので、、、)
ちなみに当店では下記のように同じ太さの絹糸とお客さまに説明しております。
同じ太さに2種類の呼び方とは、、、解りにくいですね、、、すみません。
手引真綿5匁=手引真綿1600回
手引真綿6匁=手引真綿1300回
手引真綿7匁=手引真綿1100回
このように?ホント多くの方に人気のある手引真綿糸ですが、ただその
不均一さ、節の大きさにより経糸(たていと)にはあまり向かない糸でもあります。でも人間の欲望は出来ないことならなおさらやりたいという願
望にお答えするために生まれた糸があります。
それが、ホームページ上で掲載されている手引真綿5匁タスキです。
この糸
は手引真綿5匁に28中の生糸を2本、2行程で付けることにより包み込んであります。
(繊度平均250デニール)しかも真綿糸には使いやすく&出来る限り光沢を残す為、少しだけ撚りをかけております。
経糸、緯糸共にこの糸を使われて織物を作られている方もいらっし
ゃいます。
経糸にする際はより使いやすくする為に糊を付けているようです。
ちなみにもう少し細い
4.5匁に21中生糸を2本付けた糸
3.5匁に21中生糸を4本付けた糸
も有りますよ!
以上宣伝終わり!
タスキよりについてはまた後ほど説明していきますが、詳しいこと
を今知りたい方はHPの撚りのお話をご覧下さい!
※これらは2000年6月11日に西陣の糸屋が発行したメールマガジンを変更した内容です。
ページ内の文章・写真・画像の一切の転載を禁止します。著作権は有限会社吉川商事にあります。
このページ記載の内容や新着情報は無料でご購読いただけます。
最終更新日2012年2月
|